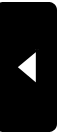http://www.kikuchi-kensetsu.co.jp/index.php
2009年07月25日
2009年07月18日
基礎工事着工です。
今日から三島市S様邸基礎工事着工です。


先日、地盤調査を行った結果は、
粘性土の土質で、良好な地盤でした。
基礎工法はベタ基礎で施工することになりました。
今日から三島展示場では『展示場内覧会』と『住宅設備まるごとプレゼント』の
イベントを行っております。
ぜひ三島展示場へお越しください。

先日、地盤調査を行った結果は、
粘性土の土質で、良好な地盤でした。
基礎工法はベタ基礎で施工することになりました。
今日から三島展示場では『展示場内覧会』と『住宅設備まるごとプレゼント』の
イベントを行っております。
ぜひ三島展示場へお越しください。
2009年07月17日
2009年07月17日
完成外観集!!
弊社でお建ていただいたお客様の完成外観写真の一部をアップしてみました
注文建築ならではの個性溢れる様々な意匠の外観が造り出せます
皆様のお好みはどんな意匠の外観ですか??

総2階大屋根でまとまっている外観。外装はサイディング貼りで、1階部分には紺色の木目調を使用し、2階部分に白色のものを使い、屋根は洋瓦(メタリック色)を葺いてあります。シンプルですが、最近はこのモノトーンの雰囲気は人気がありますね

同じくサイディングでまとめた外観。こちらはブラウンを基調とした意匠になっています。屋根には薪ストーブの煙突が伸びています。煙突も丸型のもので外にそのまま出すものと、この意匠のように外装材と同じもので角型に包んで出す形で雰囲気が変わってきます。

こちらは和風の意匠。外装は左官下地のソフトリシン吹き付け仕上げ。独特の質感と『和』の雰囲気が感じます。間取りで1,2階を総二階では無く、変化を付けてあげると、このように下屋根が出来ます。
昔からの和風建築では日本は雨が多い土地柄なので軒やケラバの出を深くし、2階を1階より小さくして下屋根を付けていたのも、外装に直接雨がかかって建物の寿命が短くならないようにと工夫されています。
弊社の建物にもこの考えが基本にあるため、軒やケラバの出は隣地との境界線までの広さとの兼ね合いも有りますが極力出すような考えを基本にご提案しています。

同様に和風の意匠。外装はモルタル下地ソフトリシン吹き付け仕上げになっています。
総二階ではなく、母屋下がりの下屋根を造りその部分が吹き抜けのリビングになっています。薪ストーブの煙突が吹き抜けの天井から屋根に出ています。
ベランダにはアルミ製手摺りと木目ラミネートされた樹脂パネルを使用し、風通しも良くデザイン的にもアクセントになっています。

本格和風の意匠。屋根は和瓦葺き入母屋造りになっています。玄関庇にも杉磨き丸太柱、桁を使用し銅板で葺き、格式を高めた雰囲気の意匠になっています。こちらの外装はモルタル下地吹きつけソフトロール仕上げ(吹きつけパターンでツブツブをつけてローラーで仕上げたもの)を仕様しています。
皆様も個性豊なマイホームを注文建築で建てませんか?

注文建築ならではの個性溢れる様々な意匠の外観が造り出せます

皆様のお好みはどんな意匠の外観ですか??
総2階大屋根でまとまっている外観。外装はサイディング貼りで、1階部分には紺色の木目調を使用し、2階部分に白色のものを使い、屋根は洋瓦(メタリック色)を葺いてあります。シンプルですが、最近はこのモノトーンの雰囲気は人気がありますね

同じくサイディングでまとめた外観。こちらはブラウンを基調とした意匠になっています。屋根には薪ストーブの煙突が伸びています。煙突も丸型のもので外にそのまま出すものと、この意匠のように外装材と同じもので角型に包んで出す形で雰囲気が変わってきます。
こちらは和風の意匠。外装は左官下地のソフトリシン吹き付け仕上げ。独特の質感と『和』の雰囲気が感じます。間取りで1,2階を総二階では無く、変化を付けてあげると、このように下屋根が出来ます。
昔からの和風建築では日本は雨が多い土地柄なので軒やケラバの出を深くし、2階を1階より小さくして下屋根を付けていたのも、外装に直接雨がかかって建物の寿命が短くならないようにと工夫されています。
弊社の建物にもこの考えが基本にあるため、軒やケラバの出は隣地との境界線までの広さとの兼ね合いも有りますが極力出すような考えを基本にご提案しています。
同様に和風の意匠。外装はモルタル下地ソフトリシン吹き付け仕上げになっています。
総二階ではなく、母屋下がりの下屋根を造りその部分が吹き抜けのリビングになっています。薪ストーブの煙突が吹き抜けの天井から屋根に出ています。
ベランダにはアルミ製手摺りと木目ラミネートされた樹脂パネルを使用し、風通しも良くデザイン的にもアクセントになっています。
本格和風の意匠。屋根は和瓦葺き入母屋造りになっています。玄関庇にも杉磨き丸太柱、桁を使用し銅板で葺き、格式を高めた雰囲気の意匠になっています。こちらの外装はモルタル下地吹きつけソフトロール仕上げ(吹きつけパターンでツブツブをつけてローラーで仕上げたもの)を仕様しています。
皆様も個性豊なマイホームを注文建築で建てませんか?

2009年07月16日
左官屋さん工事中です。
裾野のT様邸の左官工事をしています。

右側の壁は漆喰を塗っています。
やっぱり塗り壁はいいですね。このT様邸のリビングはコテで平な壁に仕上げましたけど
コテを使って色々な表情の壁に仕上げることが出来るのもいいところです。
手形を記念に残したりもできますしね。皆さんもぜひ塗壁にしませんか?
右側の壁は漆喰を塗っています。
やっぱり塗り壁はいいですね。このT様邸のリビングはコテで平な壁に仕上げましたけど
コテを使って色々な表情の壁に仕上げることが出来るのもいいところです。
手形を記念に残したりもできますしね。皆さんもぜひ塗壁にしませんか?
2009年07月14日
地盤調査です。
今日は三島市S様邸の地盤調査を行いました。


地盤調査は、スウェーデン式サウンディング試験機を用いて調査します。
この地盤調査結果を見て地盤の改良工事が必要なのか?
また建物基礎工法を検討して
建設地の地盤に適した基礎工法を決めていきます。
地盤調査は、スウェーデン式サウンディング試験機を用いて調査します。
この地盤調査結果を見て地盤の改良工事が必要なのか?
また建物基礎工法を検討して
建設地の地盤に適した基礎工法を決めていきます。
2009年07月13日
2009年07月11日
2009年07月07日
設計打ち合わせ。
今日は先月ご契約をいただいた三島市のお客様の2回目の設計打ち合わせでした。
内容としてほぼ図面内の全容のお打ち合わせが出来て、次回はその図面修正の確認を行うところにまで至りました。
設計担当の武〇さんもここまで順調に進むとは予想していなかったみたいでした。
僕もまさか2回目のお打ち合わせで電気関連、設備関連から色等の仕様決めまで終わるとは思っておらず 終始、お客様にリードしていただいた感じでした。
終始、お客様にリードしていただいた感じでした。
とは言ってもこれからずっとお住まいになるマイホームの大切なお打ち合わせですので修正点や契約内容と図面内容との整合性に不備が無いかどうかこれからしっかり確認して、納得された図面で承認していただきたいですね
設計打ち合わせがここまで進んでくると今度は着工して工事が進むのが楽しみになってきますね
今日は本当にお疲れ様でした
明日は営業所もお休みを頂きます。僕達営業マンも英気を養って今週末に備えたいと思います
内容としてほぼ図面内の全容のお打ち合わせが出来て、次回はその図面修正の確認を行うところにまで至りました。
設計担当の武〇さんもここまで順調に進むとは予想していなかったみたいでした。
僕もまさか2回目のお打ち合わせで電気関連、設備関連から色等の仕様決めまで終わるとは思っておらず
 終始、お客様にリードしていただいた感じでした。
終始、お客様にリードしていただいた感じでした。とは言ってもこれからずっとお住まいになるマイホームの大切なお打ち合わせですので修正点や契約内容と図面内容との整合性に不備が無いかどうかこれからしっかり確認して、納得された図面で承認していただきたいですね

設計打ち合わせがここまで進んでくると今度は着工して工事が進むのが楽しみになってきますね

今日は本当にお疲れ様でした

明日は営業所もお休みを頂きます。僕達営業マンも英気を養って今週末に備えたいと思います

2009年07月03日
2009年07月02日
2009年06月29日
ムク無垢建築!!
現在、弊社で建築中の建物の様子です。今日も大工さんが暑い中、一生懸命やってくれています

吹き抜けの様子。外周部に入れられたロックウール断熱材が見えます。

以前に紹介した檜の丸太を利用した羽目板です。ポイントとして部屋の一部分に使用されています。

吹き抜けの様子。外周部に入れられたロックウール断熱材が見えます。
以前に紹介した檜の丸太を利用した羽目板です。ポイントとして部屋の一部分に使用されています。
2009年06月22日
お寺建築中です。
伊豆長岡のお寺の庫裏と客殿の新築工事が進行中です。

完成は9月の末の予定で、今は大工工事の真っ最中です

柱は丈三(4m)の長さの檜の無垢材で、4寸と五寸の太さを使っています。
天井が高くて広々した空間のが出来上がります。

完成は9月の末の予定で、今は大工工事の真っ最中です
柱は丈三(4m)の長さの檜の無垢材で、4寸と五寸の太さを使っています。
天井が高くて広々した空間のが出来上がります。
2009年06月19日
続!匠の技編。
菊池建設の顔でもあります玄関下屋根(土庇)の様子を紹介します。

長さ4.5間(8.19m)の杉無垢磨き丸桁です。

90°折れ曲がる寄せ棟部分です。杉無垢磨き丸隅木、丸桁、丸柱と丸太同士を納める匠の技!(丸太材や角の材料でもただ直線的に切り落として取り付けるのではなく、木のクセ等を見て微妙な曲がりを合わせる仕事をヒカリ仕事、ヒカリ付ける等といいます。)

少し判りづらいですが、下屋根先端部分。(この下屋根の屋根材料は銅板で仕上ます。この部分を唐草と呼びます。)

そして工事途中ですが、銅板仕上げの下地の防水シートを張り込んだ状態です。
長さ4.5間(8.19m)の杉無垢磨き丸桁です。
90°折れ曲がる寄せ棟部分です。杉無垢磨き丸隅木、丸桁、丸柱と丸太同士を納める匠の技!(丸太材や角の材料でもただ直線的に切り落として取り付けるのではなく、木のクセ等を見て微妙な曲がりを合わせる仕事をヒカリ仕事、ヒカリ付ける等といいます。)
少し判りづらいですが、下屋根先端部分。(この下屋根の屋根材料は銅板で仕上ます。この部分を唐草と呼びます。)
そして工事途中ですが、銅板仕上げの下地の防水シートを張り込んだ状態です。
2009年06月14日
今も継承される匠達の技。
現在、施工中のお客様の材料の加工、建て方の様子のひとコマを紹介します。
創業以来、技術の伝承を続けてきた社員大工さんの作業風景です。着々と若い匠達が育っています。

加工され、積まれた状態の小屋の松タイコ梁。

梁同士の渡りあご部分の接合部のコミ栓。

隅木。プレカットでは見られない匠の墨付け、刻み加工が見られます。

作業風景の全景。

研ぎ澄まされた匠の鑿(ノミ)。

自然の木の曲がりを考慮した加工。見事に納まってます。

先述した梁同士の渡りあごの接合部分。

棟が上がりました ここからは現地で取付けをするこれまた凄腕のベテラン大工棟梁さんが造作工事に入り、木工事の完了まで作業を進めて行きます。
ここからは現地で取付けをするこれまた凄腕のベテラン大工棟梁さんが造作工事に入り、木工事の完了まで作業を進めて行きます。

そして少し飛びますが、屋根瓦が乗った状態です。
創業以来、技術の伝承を続けてきた社員大工さんの作業風景です。着々と若い匠達が育っています。
加工され、積まれた状態の小屋の松タイコ梁。
梁同士の渡りあご部分の接合部のコミ栓。
隅木。プレカットでは見られない匠の墨付け、刻み加工が見られます。
作業風景の全景。
研ぎ澄まされた匠の鑿(ノミ)。
自然の木の曲がりを考慮した加工。見事に納まってます。
先述した梁同士の渡りあごの接合部分。
棟が上がりました
 ここからは現地で取付けをするこれまた凄腕のベテラン大工棟梁さんが造作工事に入り、木工事の完了まで作業を進めて行きます。
ここからは現地で取付けをするこれまた凄腕のベテラン大工棟梁さんが造作工事に入り、木工事の完了まで作業を進めて行きます。そして少し飛びますが、屋根瓦が乗った状態です。


 の中の地鎮祭でしたが無事に終わりました。
の中の地鎮祭でしたが無事に終わりました。
 。
。